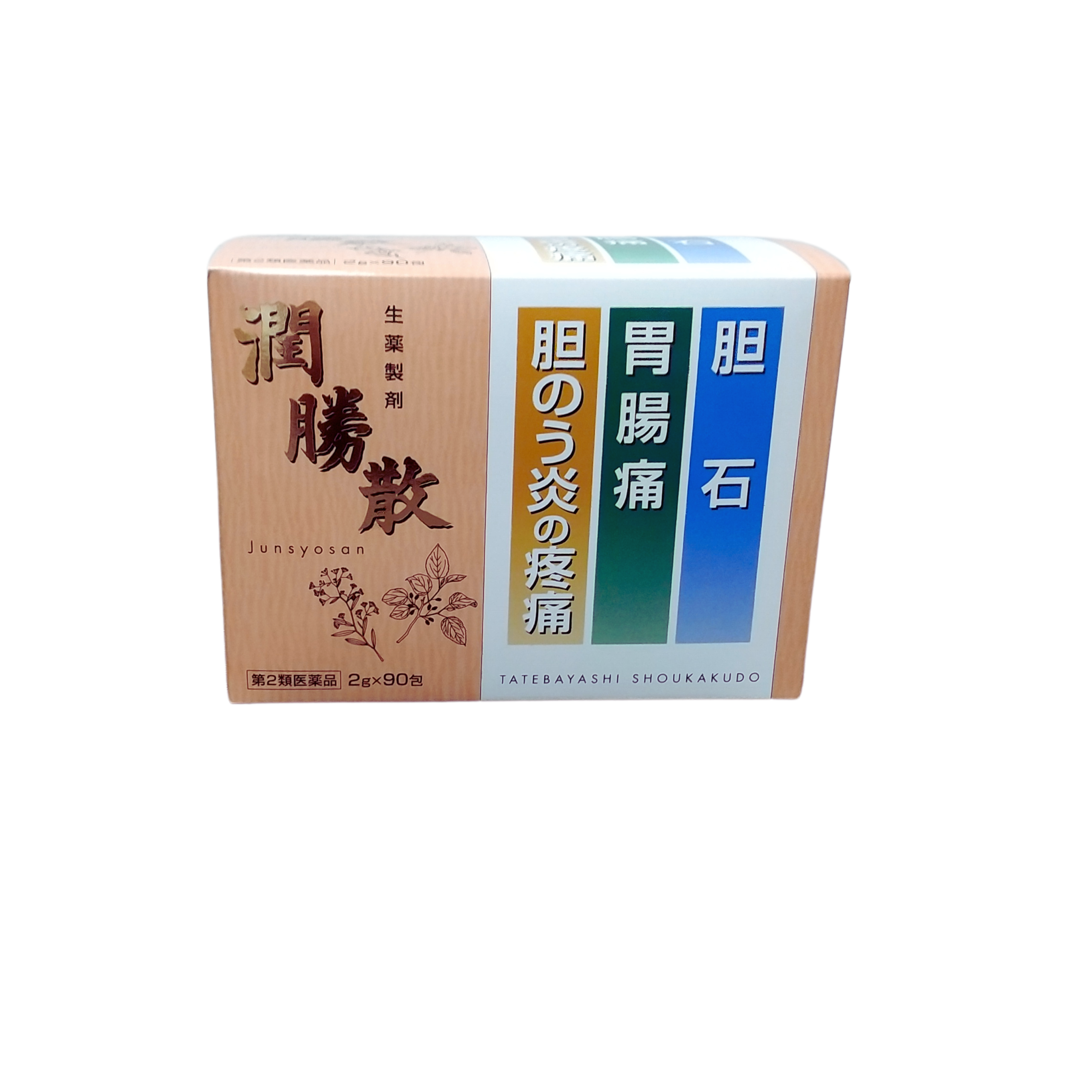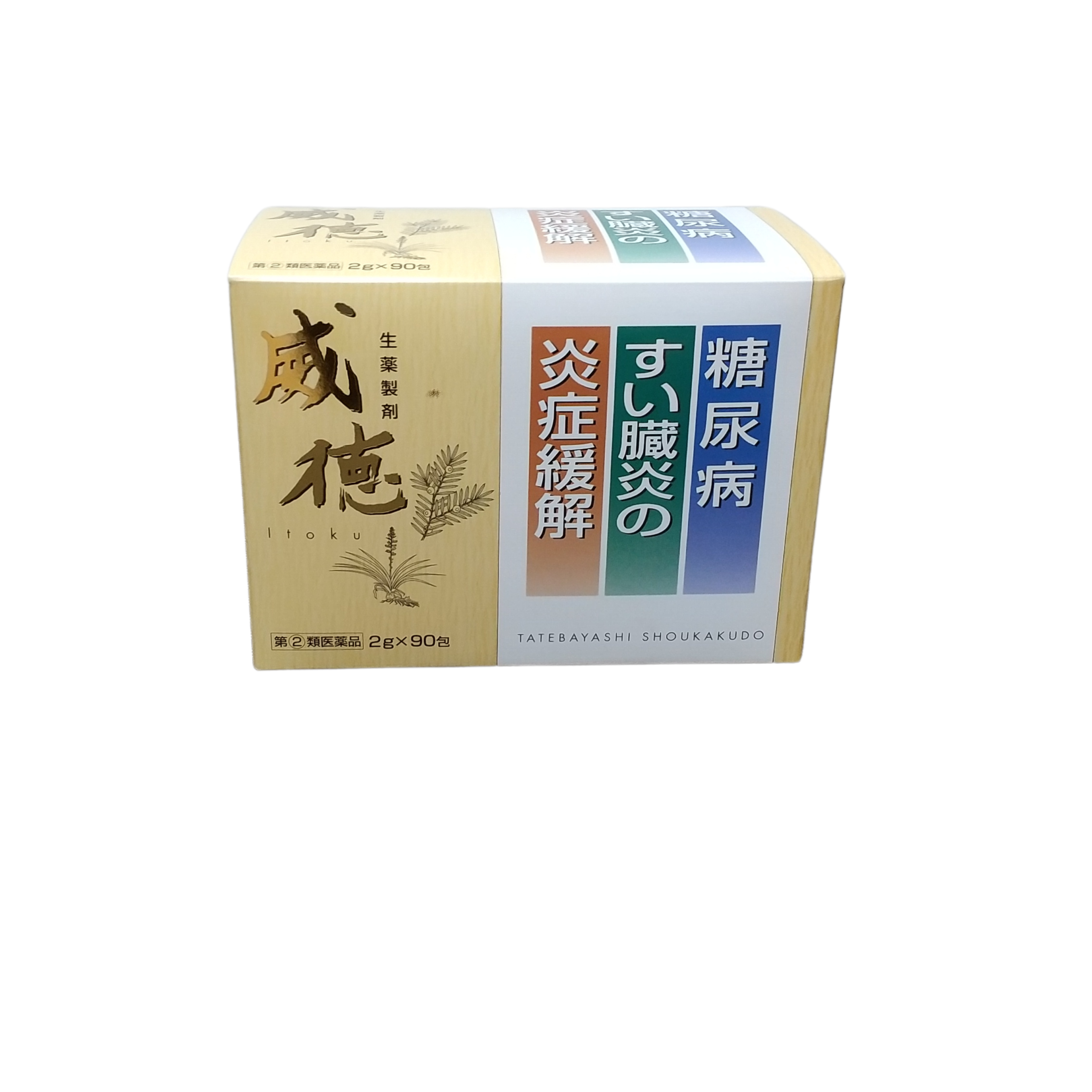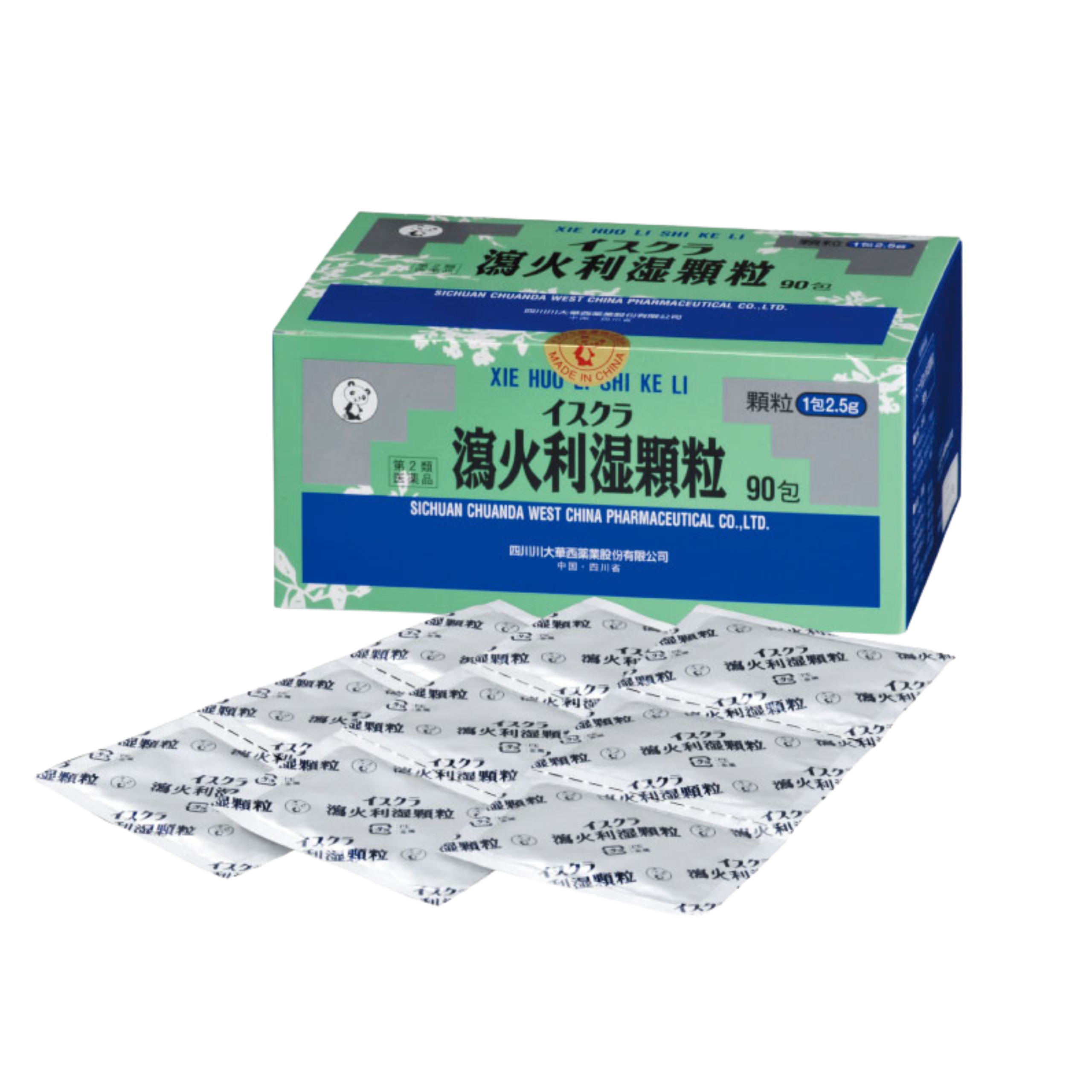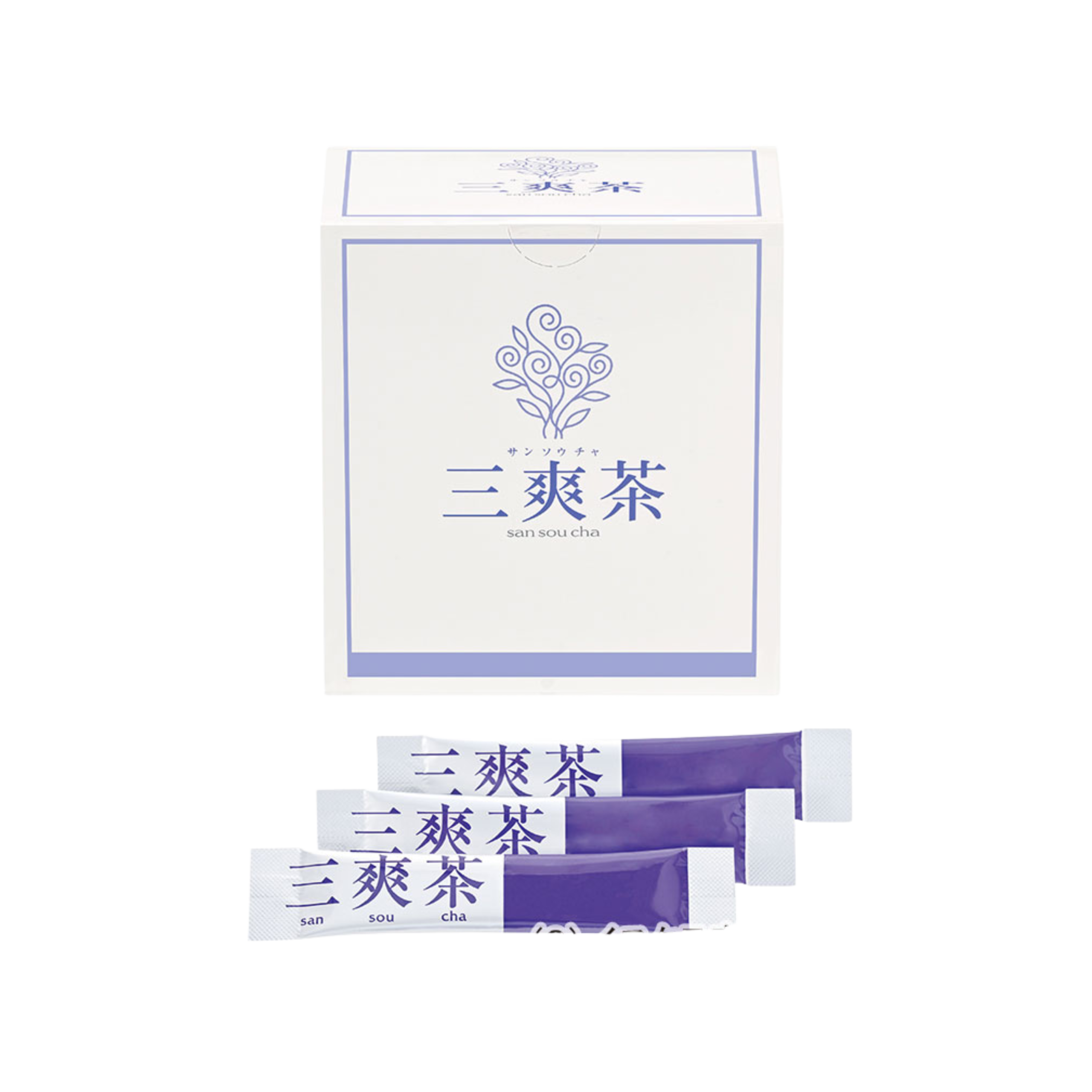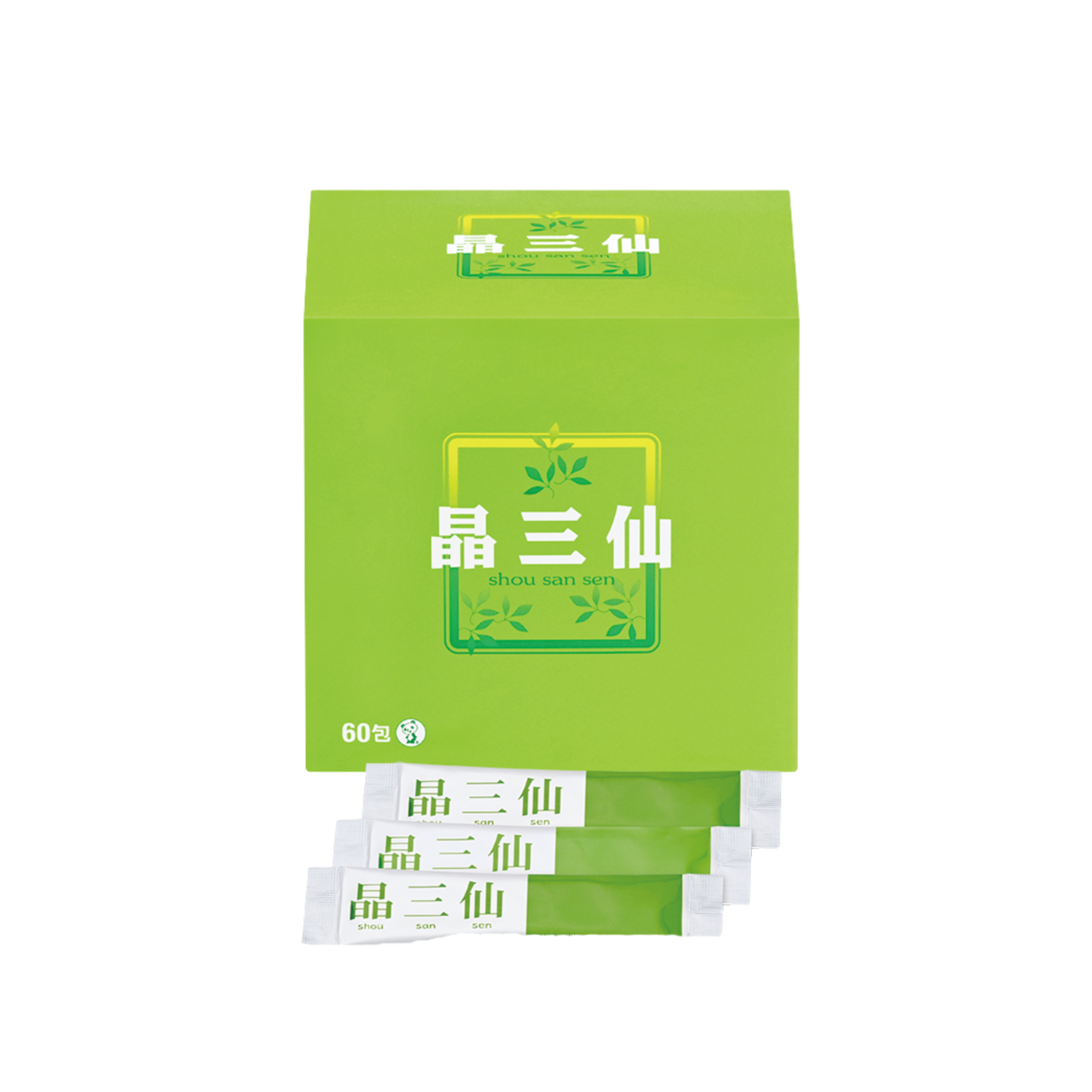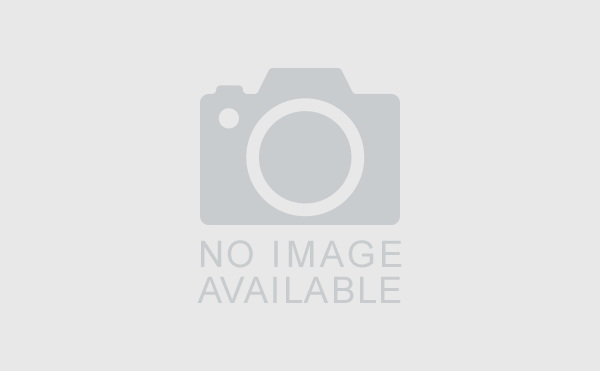ダイエット
肥満の症状
「肥満」は体の中の脂肪組織が増加した状態をいい、脂肪組織の蓄積は新陳代謝のバランスを崩し、さまざまな病気を引き起こします。心臓病、動脈硬化、糖尿病、高脂血症などの成人病を始め、疲労や無気力、不眠により生活の質が下がったり、ひざや腰を痛めやすくなるなど、徐々に生活の自由が奪われていきます。
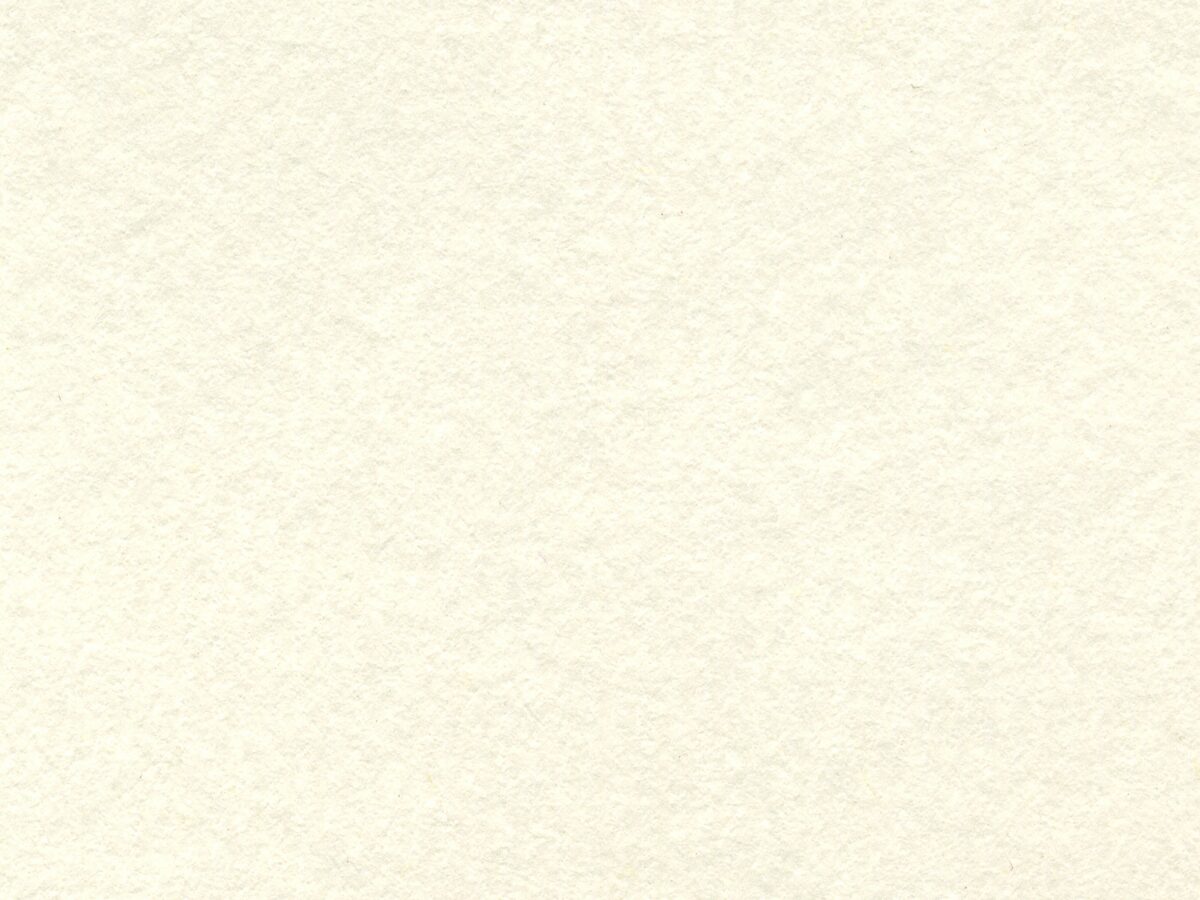
中医学で出来る肥満対策
運動や節制が辛くなり挫折したり、せっかく痩せても、体力が落ちて風邪をひきやすくなったり、皮膚や髪がパサパサになったり..。無理なダイエットを繰り返すと、代謝がさらに低下し、痩せにくくなるだけでなく、健康面にも支障がでます。中医学では、体質が肥満を作ると考え、体質に合わせた治療を行います。体質を改善し、体のバランスが整うと、肥満だけではなく、日頃からかかえていた他の不調の改善にも役立ち、全体の健康につながります。
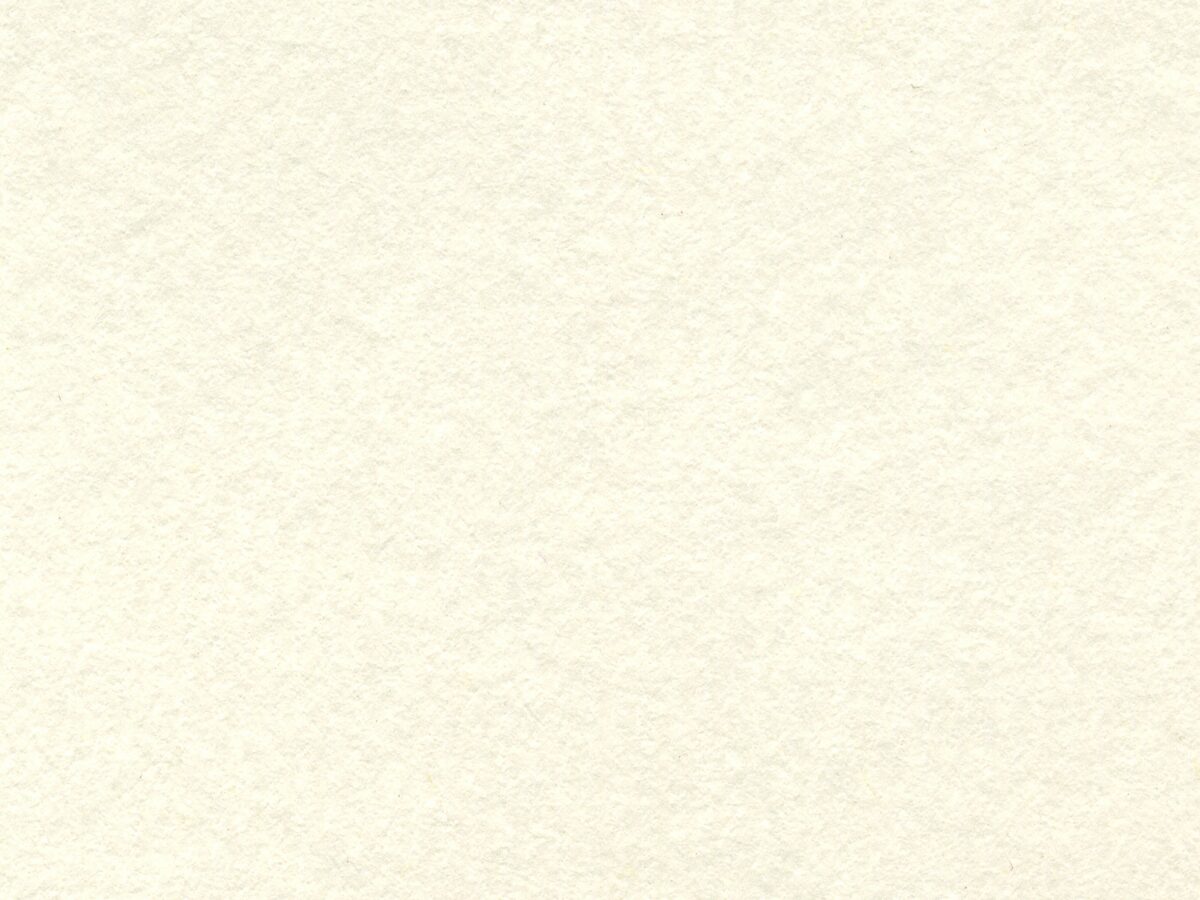
中医学でみる肥満の原因
(1)遺伝
遺伝的に肥満の体質、陽(活動的、外交的、せっかち、怒りっぽい)の体質があると、胃熱が旺盛になり食欲が暴走し、必要以上に食べることとなる。脂っこいもの、甘いもの、味の濃い物、冷たい物、乳製品、酒などは、ドロドロとした「痰湿(たんしつ)」になりやすく、体に蓄積されて肥満となる。
(2)飲食不節
中医学では「脾は湿を憎む(ひはしつをにくむ)」といい、脾(胃腸など消化機能全般)は湿邪を受けると働きが低下すると考える。そのため湿気の多い夏や梅雨時に胃腸炎がはやるとされる。また、冷たいもの、甘いもの、酒、乳製品などは「湿」を生む食べ物とされ、食べ過ぎて「湿」がたまると脾のはたらきが低下し、飲食物から栄養やエネルギーを作れなくなり、体が養えず、全体の働きが停滞し、老廃物や余分な水分を代謝するエネルギーも減り、痰湿がたまり肥満となる。
(3)運動不足
運動不足により、気血のめぐりが低下し、飲食物が体の中に蓄積するとともに体のバランスが崩れ、代謝が低下し、ドロドロした水分(痰湿)が皮膚、筋肉、臓腑、経絡などに蓄積されて肥満となる。気をつけなければいけないのは、めぐりの低下が長びくと、痛みに変わるということ。腰や関節、足などが痛み、運動できないという悪循環におちいり、ダイエットと並行し、気血をめぐらせ痛みをとる漢方治療をすることとなるので治療も長くなる。そうなる前にこまめに体を動かすことが大切に。
(4)加齢
肥満は年齢と深く関係がある。40歳を過ぎて体重が増えてくるのは「腎」の弱りにともない、「脾」のはたらきが低下し、飲食物を充分に代謝できなくなることや、「腎」の弱りから精気が不足すると水が滞り、内分泌や代謝にも影響し、尿中から老廃物も排出されにくくなる。先天の精をたくわえる「腎」と後天の精をつくる「脾」から代謝のエネルギーは作られるため、脾と腎を同時にケアすることが大切となる。
また更年期にさしかかっている場合は、ホルモンバランスの乱れにより「肝」と「腎」のはたらきが低下し、気血津液のめぐりが滞り、老廃物がたまりやすくなる。「肝」は気候や環境の変化に弱く、ストレスなどでも悪化するので、ストレス解消法を身につけたり、完璧主義をやめるなど、思考のシフトも大切となる。
肥満の体質別原因
①痰湿内盛(たんしつないせい)
【主な症状】
| ✅痰が多い(のどに痰がからむ) |
| ✅胸やお腹が張る |
| ✅食後に吐き気や胃酸が上がる |
| ✅満腹感がなく、いつまでも食べ続ける |
| ✅体が重い |
| ✅いびきをかく |
| ✅舌の苔が厚い |
【治療原則】
化痰利湿・減肥
脂っこいもの、あまいもの、冷たいもの、生もの、アルコールなどの取り過ぎにより、ドロドロとした老廃物「痰湿(たんしつ)」が生じる。痰湿は気血のめぐりを低下させ、膨満感や詰まりを起こす。またこもった痰湿が熱に変化して胃熱が盛んとなり、一時的に食欲が亢進。そのため食事の量がますます増えて、さらに痰湿が生じる。
たまった痰や湿を取り去ることや、舌苔が黄色い、口臭が強いなど痰湿が熱と化している場合は清熱も必要となる。

②脾気虚弱(ひききょじゃく)
【主な症状】
| ✅疲れやすく、すぐに息が切れる |
| ✅食事量は多くない |
| ✅カゼをひきやすい |
| ✅まぶたや顔がたるんでいる |
| ✅寝ても寝ても眠い |
| ✅よだれがよく出る |
| ✅舌の両脇に歯のあとがつく |
【治療原則】
健脾益気・減肥
「脾」のはたらきが低下し、エネルギー不足により湿や痰を動かす力が弱くなり、体に老廃物やよけいな水分がたまった状態。脾の弱りから、飲食物から栄養やエネルギーを作り出せずに疲れやすくなったり、エネルギー不足が原因でむくんだり、筋肉のゆるみやたるみ、だるさが生じる。水を飲んだだけでも太る。
エネルギーを増やし、脾のはたらきを高め、痰湿がたまらないようにするとともに、すでにたまっている湿や痰を取り去る傾向の漢方薬を使用する。

③瘀血疎滞(おけつそたい)
【主な症状】
| ✅生理痛がある。経血に塊が混ざる |
| ✅頭痛や肩こりで刺すような痛み |
| ✅シミやくすみ、目の下にクマ |
| ✅血中コレステロールや中性脂肪が高い |
| ✅足に静脈瘤がある |
| ✅手足が冷える |
| ✅舌の裏側の血管が浮き出ている |
【治療原則】
活血化瘀・行気和血
血のめぐりが停滞し、血管や臓腑に脂肪や余分や水分がたまり、運航の邪魔となり、さらにめぐりを低下させる。血は細胞一つ一つに酸素や栄養を運び、体のすみずみにまで血が行き届いてこそ役割が果たせるが、めぐりの悪さから必要な栄養分が届けられなくなり体を養えず、筋肉や腰の痛み、ひざの痛みなど痛みとして表れる。
血のめぐりをよくするだけでなく、飲食の不摂生で酷使され続けた血管をケアし、しなやかにすることが大切となる。

④肝気鬱血(かんきうっけつ)
【主な症状】
| ✅食欲に波がある |
| ✅すぐイライラする |
| ✅胸やわき腹が張る |
| ✅寝つきが悪い |
| ✅生理周期が乱れている |
| ✅便秘 |
| ✅舌の両脇が赤い |
【治療原則】
疎肝理気・清熱
ストレスで「肝」のはたらきが低下すると、気血津液を動かす司令塔の役割に支障が生じ、めぐりの停滞が起こる。また「肝」は女性ホルモンや自律神経系、情緒の安定にも関わるために、気分により食欲の振れ幅が大きくなる。さらに「肝」と「脾」は相克関係にあり、肝の不調は脾も弱らせるため、消化機能が落ちて痰や湿がたまりやすくなる。
「肝」をリラックスさせ、気のめぐりをよくし、イライラで熱がこもっている場合は清熱をする。生理前やストレスがかかると暴飲暴食する傾向があるので、心身を休めることが大切に。

⑤肝胆湿熱(かんたんしつねつ)
【主な症状】
| ✅頭やわきに汗をかき、臭いが強い |
| ✅口の中が苦く、粘っこい |
| ✅よく悪夢にうなされる |
| ✅目の充血や顔が赤くなる |
| ✅おりものが黄色く臭う、陰部がかゆい |
| ✅便器につくベタベタした便で臭いが強い |
| ✅舌が紅く、苔が黄色い |
【治療原則】
清熱利湿・利胆清熱
ストレス、過労、暴飲暴食、酒の過剰摂取などで、湿熱がたまり「肝」に負担がかかると、その不調は肝の腑である「胆」も影響を受け、胆汁の流れを滞らせる。肝胆の経絡に熱がこもるので、目、わき腹、陰部などに症状が現れる。さらに肝胆湿熱は脾にも影響し、消化吸収を低下させるので、飲食物を消化できずにためこみやすくなる。
肝胆にこもった熱や痰湿を除き、消化を助ける漢方を使用する。暴飲暴食やストレスは、肝胆の働きを弱める原因となるので、食生活と生活習慣の見直しも大切に。

⑥脾腎陽虚(ひじんようきょ)
【主な症状】
| ✅腰の痛みやだるさ |
| ✅夜中に何度もトイレに行く |
| ✅腰や腹部が冷える |
| ✅疲れやすい |
| ✅全身がむくむ |
| ✅お腹に力がなく、ポチャポチャしている |
| ✅舌が広がり、両側に歯の痕がつく |
【治療原則】
温腎補脾・利水去湿
消化機能である「脾」と加齢により「腎」の力が弱まり、体を温めて水分を気化するエネルギーが不足している状態。温める力が弱まるので、足腰、お腹の冷え、下痢などが出てくる。冷えは胃腸のはたらきも弱め、脂っこいもの、甘い物、酒などを消化できずに生じた痰湿に冷えが加わり、より冷えを体に滞らせ、さらに代謝が低下する。
腎と脾のエネルギーを補い、はたらきを助ける漢方を使用する。胃腸に負担をかけないことと、働きすぎ、遊びすぎ、睡眠不足は腎の負担となるので、疲れたらしっかり休むことを