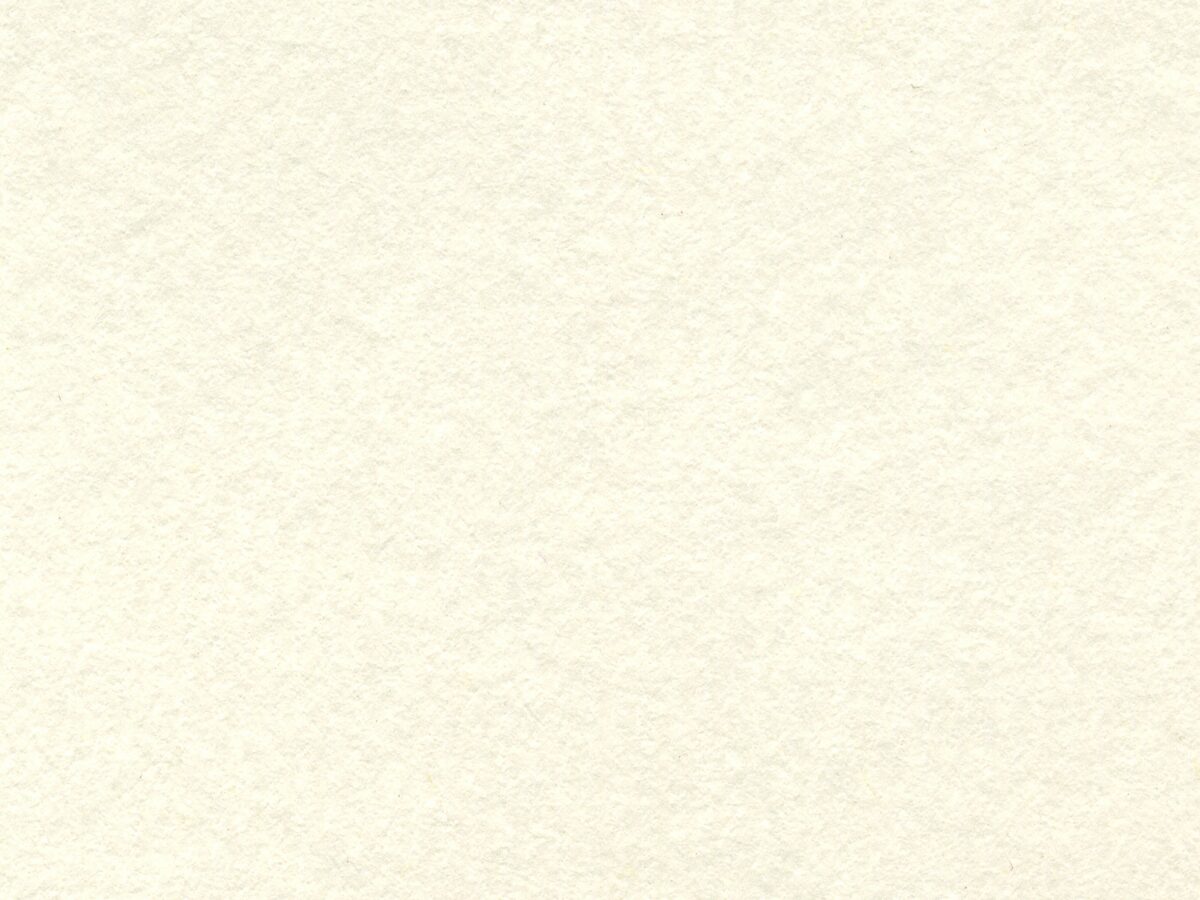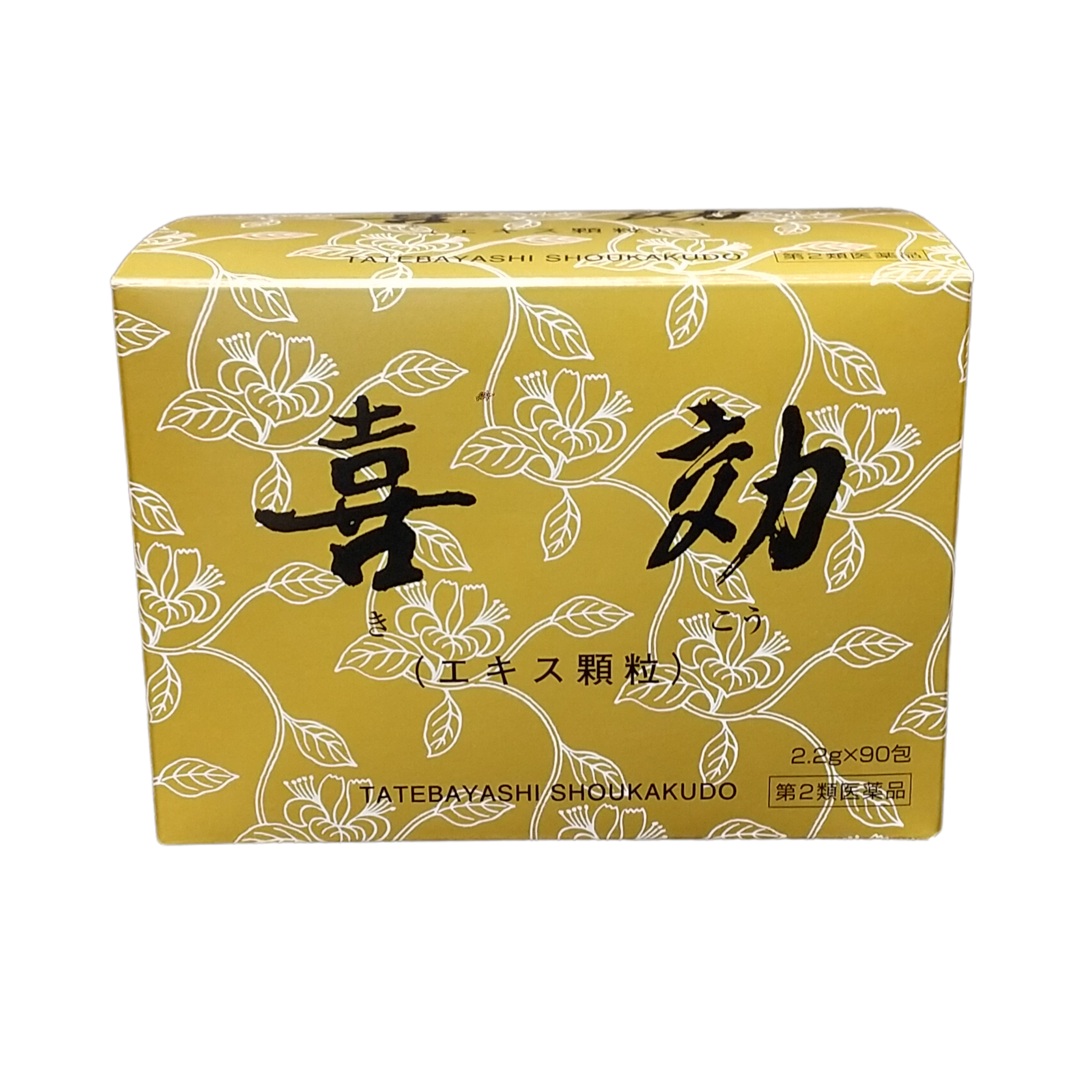生理痛
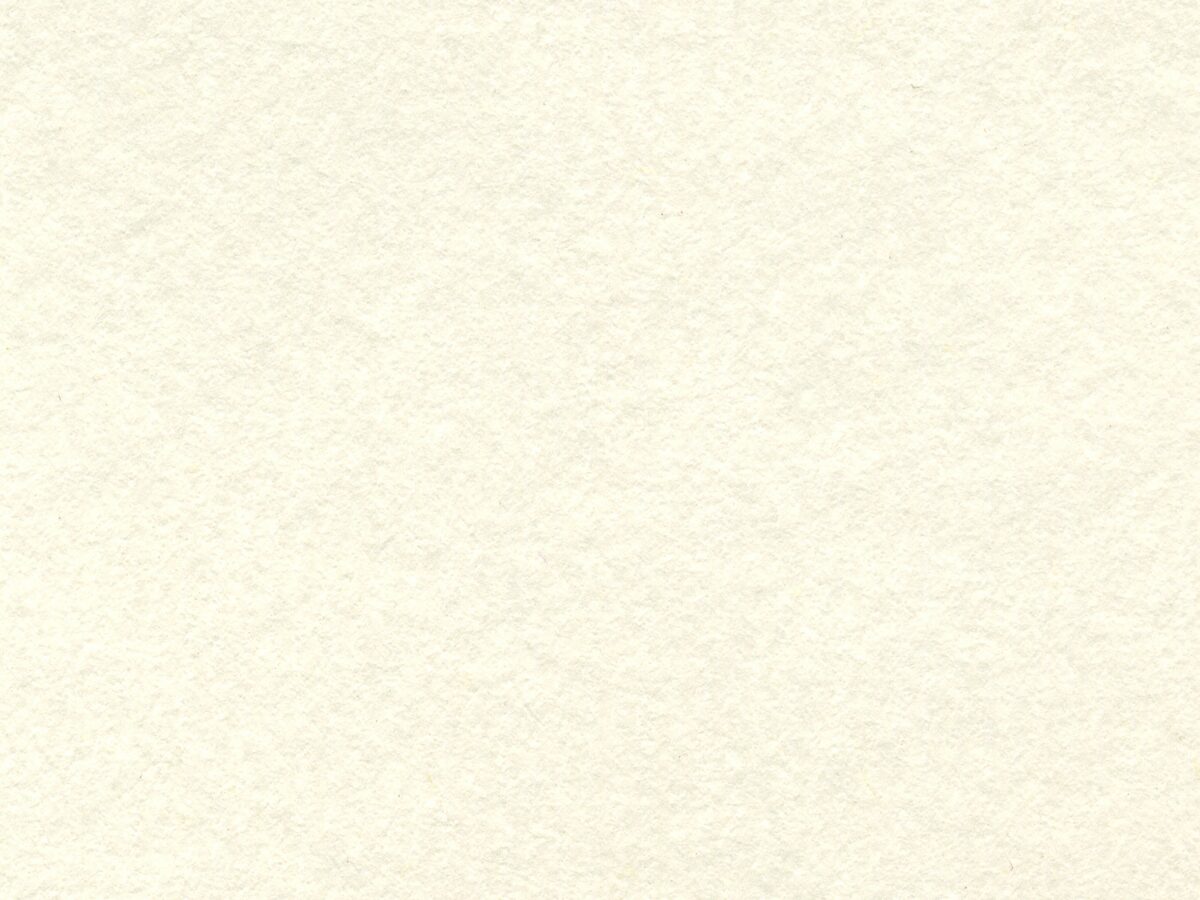
漢方では「生理痛はないのが当たり前」とされ、ある場合は治療や生活改善が必要と考えますが、実際は生理痛に悩んでいる女性は多く、痛みを我慢してやり過ごすという方もいらっしゃるのではと思います。生理痛を改善することは、妊娠、出産、授乳、更年期、閉経後と各ステージでのトラブルや婦人科疾患の予防にもつながりますので、早めの段階で体質に合ったケアを行うことが大切です。
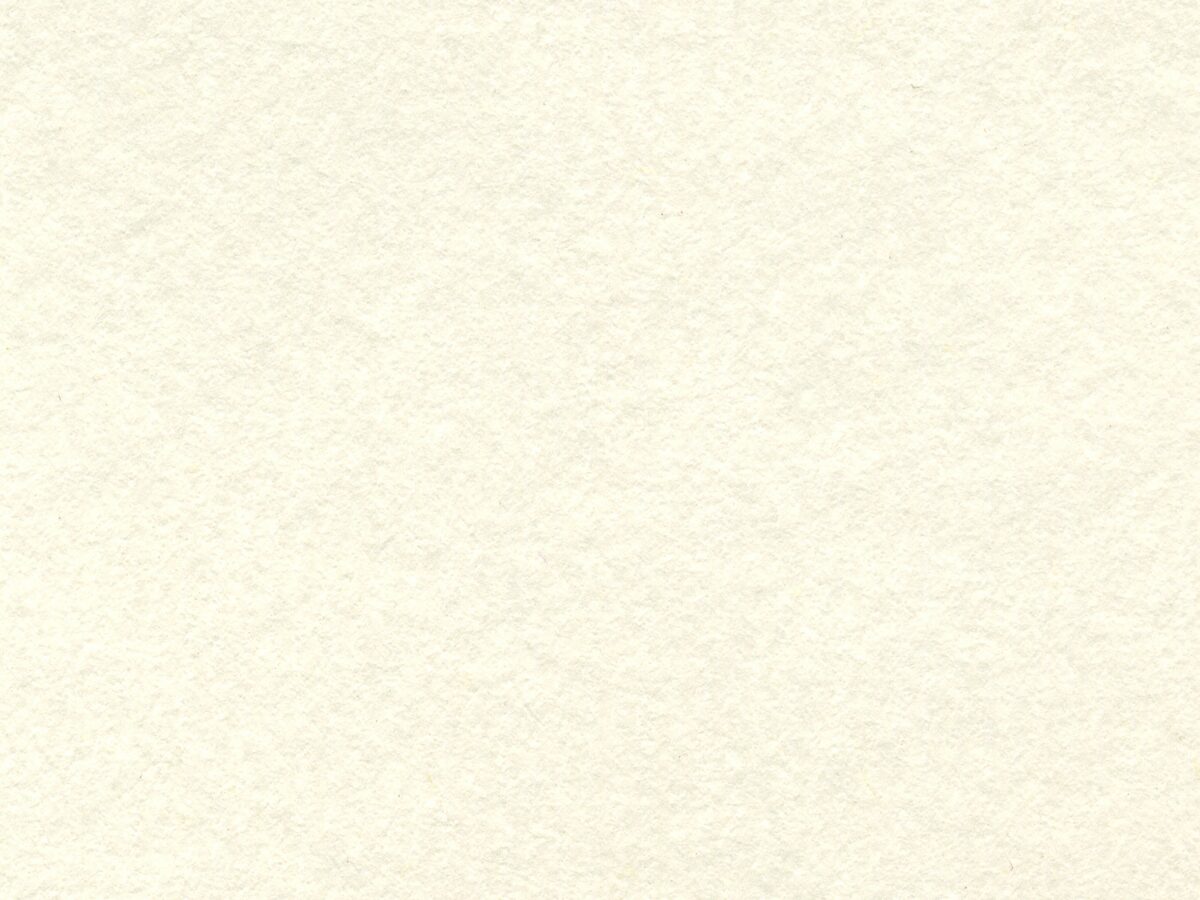
生理痛の原因は?
生理痛がひどくなる主な原因は、プロスタグランジンというホルモンの過剰分泌が挙げられます。 プロスタグランジンは、生理中に子宮内膜が剥がれる際に分泌される物質で、子宮を収縮させ経血を排出する役割がありますが、これが過剰に分泌されると、子宮の収縮が強くなり、激しい痛みを引き起こすことになります。
さらに、冷え、ストレス、緊張、食生活、睡眠不足や自律神経の乱れで痛みが起きやすくなるほか、出産経験がなく子宮口が狭い方や若い世代で臓腑が未熟なことなども原因とされます。

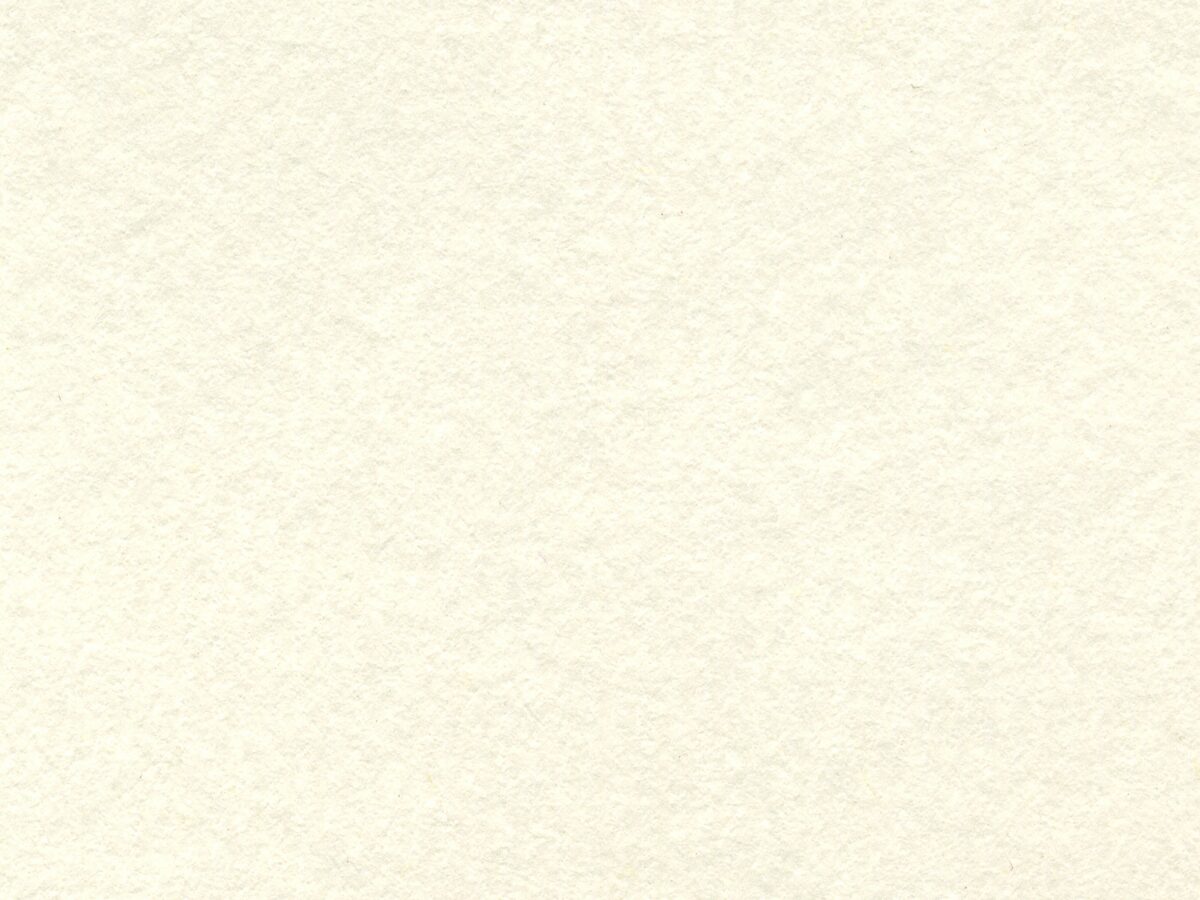
中医学でみる生理痛
中医学では痛みのタイプを大きく2つに分けます。
①実証タイプ「不通則痛(ふつうそくつう」→気血のめぐりが悪いことで起こる痛み。強い痛みが特徴で、経血にレバー状のかたまりが混ざったり経血の色が暗い。普段からストレス、冷え、運動不足、甘いものや脂っこいものを好む
②虚証タイプ「不栄則痛(ふえいそくつう)」→気血が足りないことが原因で起こる痛み。痛みは強くないが、しくしくした痛みが続く。経血の色は薄く、生理中に不安や落ち込みが強くなったり、眠りが浅くなる。疲れ、めまい、カゼ、下痢なども起こしやすい

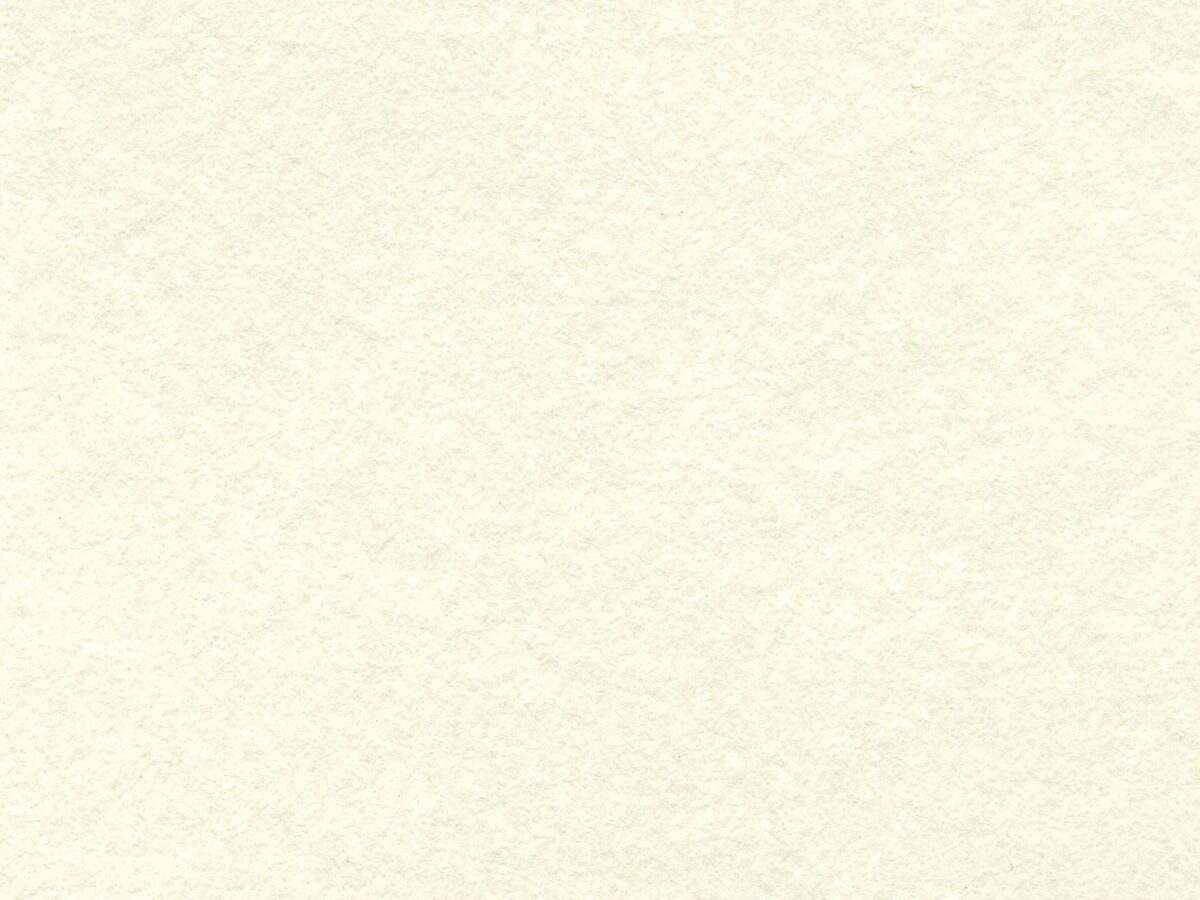
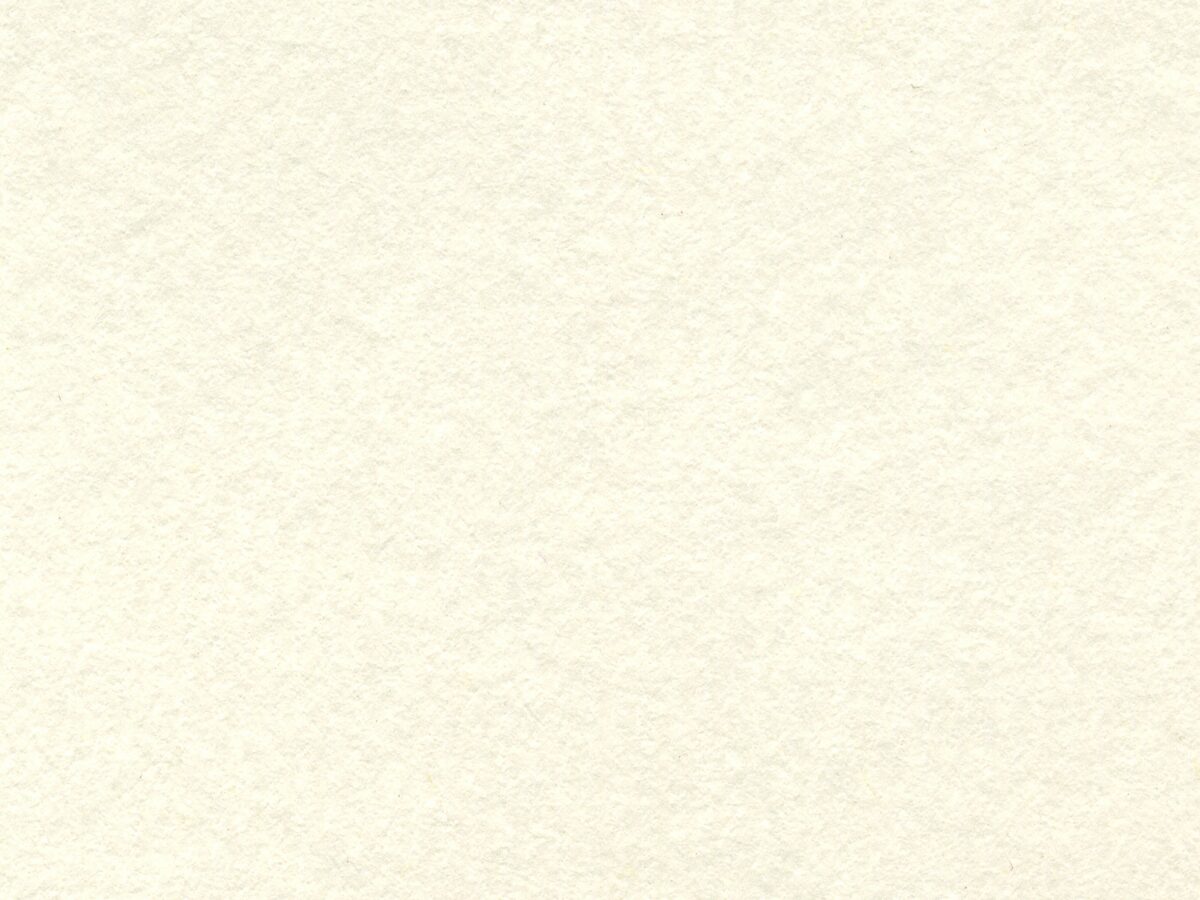
生理痛の体質別原因
①気滞血瘀(きたいけつお)
【主な症状】
| ✅生理前や生理中に下腹部が張る痛み |
| ✅ため息が多く、がまん強い |
| ✅刺すような痛み |
| ✅経血に塊が混ざる |
| ✅イライラが強い |
| ✅胸やお腹が張る |
| ✅唇や歯ぐきの色が暗い |
| ✅舌の裏側の血管が浮き出ている |
| ✅生理周期が乱れている |
| ✅子宮筋腫、腺筋症、子宮内膜症 |
【治療原則】
理気活血・化瘀止痛
生理痛の原因で比較的多いタイプ。ストレスや緊張、過度なスケジュール、自律神経の乱れなどで、気血をめぐらす「肝」の働きが低下すると、肝気が停滞し、気のめぐりが悪くなり膨満感や張る痛みが出る。さらに気のめぐりが悪くなると血を推動できなくなるため、血のめぐりも低下し、渋滞を引き起こし、痛みとなる。ストレスがたまっていることを自覚し、せめて生理期間中は無理をせず、出来るだけ好きなことをして過ごしましょう。

②寒凝胞中(かんぎょうほうちゅう)
【主な症状】
| ✅生理前や生理中に下腹部が冷えて痛む |
| ✅ひきつれるような痛み |
| ✅温めると痛みが和らぐ |
| ✅経血の色が暗く、量は少ない |
| ✅手足が冷たい |
| ✅体を冷やすファッションをしがち |
| ✅冷たいもの、野菜サラダ、スムージーをよくとる |
| ✅冷房や冬の寒さで悪化する |
| ✅よく下痢をする |
| ✅舌の色が暗い |
【治療原則】
散寒暖宮・温通血脈
「寒」は陰に属し、陰は重く沈み「寒」は「湿」と結びつきやすく、湿はどろどろと粘る性質で、寒の動きを阻害し、長時間停滞させる。子宮の中には血脈が多くつらなるので、血は寒と湿により巡りが妨げられるために痛みがおこる。
胃腸の弱い方は「湿」を生じさせやすく、生理中は出血により体が虚して、寒さの侵入をうけやすくなる。日本は島国で湿気も多いうえに、飲食店で氷水を飲み、生ものを食べる習慣もあるので、日常での過ごし方にも注意しましょう。

③気血虚弱(きけつきょじゃく)
【主な症状】
| ✅生理の後半から痛みがある |
| ✅しくしくと弱い痛みが続く |
| ✅経血量が少なく、色が淡い |
| ✅生理や不正出血がだらだら続く |
| ✅めまいや立ちくらみをする |
| ✅髪がパサパサし、枝毛や切れ毛が多い |
| ✅食が細い |
| ✅子宮内膜が薄い |
| ✅生理期間中は不安や落ち込み、眠りが浅くなる |
| ✅舌の色が淡い、舌の両わきがギザギザしている |
【治療原則】
調補気血
中医学では「胞宮(子宮など女性の臓腑)は血の海」といい、生理により出血することで、胞宮は空虚となる。臓腑を営養する血が不足することで、はたらきが低下し、弱い痛みが続くこととなる。
もともとの気血が不足しているため、いきなり血をめぐらす方法を行うと体に負担が強く、気血をさらに消耗し、悪循環となります。まずは気血を補い、生理中はしっかり眠り、エネルギーを消耗しないよう活動も控えめに。

④肝腎虚損(かんじんきょそん)
【主な症状】
| ✅生理の後半にしくしくした痛み |
| ✅腹部をさすると痛みが楽になる |
| ✅経血量が少なく、色が淡い |
| ✅腰痛や腰周辺がだるくなる |
| ✅のぼせや寝汗、微熱がある |
| ✅耳鳴りやめまい、もの忘れが多い |
| ✅目が乾き、疲れやすい |
| ✅爪が割れやすい |
| ✅生理周期が乱れている |
| ✅疲れやすく根気がない |
【治療原則】
益腎養肝・止痛
中医学では「精血同源」といい、「精」と「血」は依存しあっていると考えます。血が不足する状態が長く続くと、精も不足し、腎のはたらきが低下し、生理痛のほかに腰の痛みやだるさなど腎の症状をともなう。腎の働きが低下してくる40代から表れやすい。生まれながらに先天の精が弱く未成熟な10代の女性にも表れることがある。
血を補うとともに、腎のはたらきを助ける治療が必要。後天の精を作る胃腸を大切にし、陰の時間(夕方~夜中まで)は静かに過ごし、睡眠はしっかりとりましょう。